「THE PHILOSOPHY OF CURRY(カレー哲学)」と銘打った本が出た。俺のための本かと思った。
イギリスで出版された『THE PHILOSOPHY OF CURRY』を早速個人輸入してみたので紹介してみる。(先走って買っちゃったけど、実はKindle Unlimitedで無料で読める)
どんな本か
- ロンドン在住のフードライターか書いた「カレー哲学」の本。
- 実際は哲学書というよりは歴史書。(ただ、哲学する上で歴史の観点は欠かせないと思う)
- イギリス人の視点から見たカレー、インド料理。植民地支配を含め、Curryという言葉が背負っている歴史や重みも含めて捉えている。
- インド料理が古代から植民地時代まで歴史的にどう変化して行ったかを解説している。
- Curryとしてインド料理を離れてイギリスの食世界に定着した料理たちや、日本も含め世界に散らばるカレーを幅広く紹介。
「カレー」とは何か
「カレー」は 本当に存在するのだろうか?もしくは、それは複雑で多様な料理を過剰に単純化している不適切な言葉だとして拒否すべき言葉なのだろうか? というのが本書を貫く大きなテーマ。
日本でも「カレーとは何か」という議論はポピュラーだ。いまや「Curry」は世界中すべての大陸に存在する。しかし、その定義は難しい。過激な人の中には「カレー」という言葉自体を全否定してしまう「curry denier(カレー否定論者)」人もいる。実際この本を作る中でも、「curryという言葉が植民地支配を連想させる」とか「インド料理にはカレー以外のものもたくさんあるし、地域性を取りこぼしている」と言ってたくさんの反対意見を受けたという。
日本のカレー事情はイギリスを経由してしまっているので少し特殊だが、インド料理店で一般的に”Curry”と呼ばれるのは玉ねぎとトマトベースのものであり、多くはパンジャーブ料理やムガル料理がメインだ。
だが、Curryとひとくくりに呼ばれてしまう言葉の向こう側にインド料理のそれぞれの地域の”Curry”がある。
Regional curries are known by specific names like sabzi, shaak, salna, salan, palya, poriyal, fry, jhol, rassa, kuzhambu, saagu, erissery, gassi, pulusu and so on.
p.5
ここで上げられているのはほんの一例だが、これを全部「curry」と呼ぶのは確かに無理があると思う。でも同時に、curryと言う言葉によって見出される統一によってある世界から別の世界に接続され、概念は豊かに膨らんでいく。
ちなみにここで具体例として上げられているのはすべて、インド各地に散らばる「Curry」に相当するような汎用的な言葉だ。
カレーの定義とは
本書で著者はカレーをこう定義している。
curry is a spiced dish of indian origin or influence, in which vegetables, or meat ot other protein, are normally cooked in a pot, usually with a gravy made from tomatoes, onions, coconut, yoghurt, gram flour, nuts, cream, water or stock
p.7
日本語訳するならこんな感じだろうか。
カレーとは、トマト、玉ねぎ、ココナッツ、ヨーグルト、ひよこ豆の粉、ナッツ類、クリーム、水やだし汁で構成されたグレイビーで野菜や肉・その他のタンパク質を通常丸くて深い鍋で調理した、インド起源もしくは影響を受けたスパイス料理である。
うーん、まあまあ良い線行ってはいると思うけどどうなんですかね。同じスパイスを使った煮込み・炒め料理でもカレーとカレーじゃないものがあるのはなぜだろうか。そのへんの線引をインド的なルーツに求めすぎるとうまく説明できなくなったりする。同様に、思い出や想起をカレーの条件にするのもトートロジーの域を出ないと思う。
例えば麻婆豆腐はカレーか?と考えたときにこの定義だとカレーに当てはめることができない。
自分は麻婆豆腐はカレーだと思っているクチだが、根拠を感覚に求めてしまうのも気持ち悪いのだ。
本書の結論
カレーとはなにか?という問題提起をしたあと、話は古代インドから始まり、西洋の植民地支配、カレー粉の発明、ロンドンでのカレーハウスの話…。とお決まりの展開を見せる。最終的には世界に広がるカレーたちの紹介になっているが日本のカレー紹介箇所は薄い。日本のカレーシーンももっと面白いことになっているのにな。
本書の最終的な結論はこうだ。
カレーという言葉はもはや否定できない。もしくは、もう否定するには遅すぎる時代になってしまった。カレーという言葉をむやみに否定せず、もう曖昧でいいんじゃないかと。
それには以下のような理由をあげている。、
- 「カレー」という名前の料理がもはや世界中に広まっているのに、それが存在しないとなぜ言えるのだろうか?
- いわゆる「現地系」の料理が「カレー」よりオーセンティック、本物だと主張するのは傲慢ではないだろうか?
- カレーが植民地主義と結びつくというのならば、そのことによってもたらされた食材によって文明や料理が発達したことも否定するしかないのだろうか?
- 「インド現地にcurryはない」というのももはや昔の話だ。今では至るところで「curry」という言葉が使われている。
- カレー自体のインド料理も広く知られ、インド料理に対する認識自体が変わっている。「カレーだけがインド料理じゃない」ということはもはやわざわざ主張しなくてもいい。
雑な用語の濫用には反対だが、これには納得感がある。日本の状況を見ても同じことが言えるようにも思う。
感想
冒頭と結論部を除くと『インドカレー伝』で紹介されている内容とも被る部分が多かったが、Curryという言葉にフォーカスしてその用語自体を突き詰め、肯定的に捉えている様子が伺える。
イギリスではインドにルーツを持つ人も多いためCurryが身近だが、あくまでインド料理ベースのものが主流。モダンインディアンのお店などはたくさんあるが、ルーツはあくまでインド料理という姿勢を崩していない。
それを考えると、日本はカレーの盛り上がり方に関してかなり特殊な地域というか、はっきり言って異常だ。
結論部でも触れているが、本書はカレーに関して偏った側面からしか語られていない。一番気になるのはインド人によるカレー哲学だが、これだけ異常にカレーが盛り上がっている日本からのカレー哲学は特異点としてとても面白いものになるだろう。
今後、日本発信のカレー哲学を打ち立てていくのは我々だ。
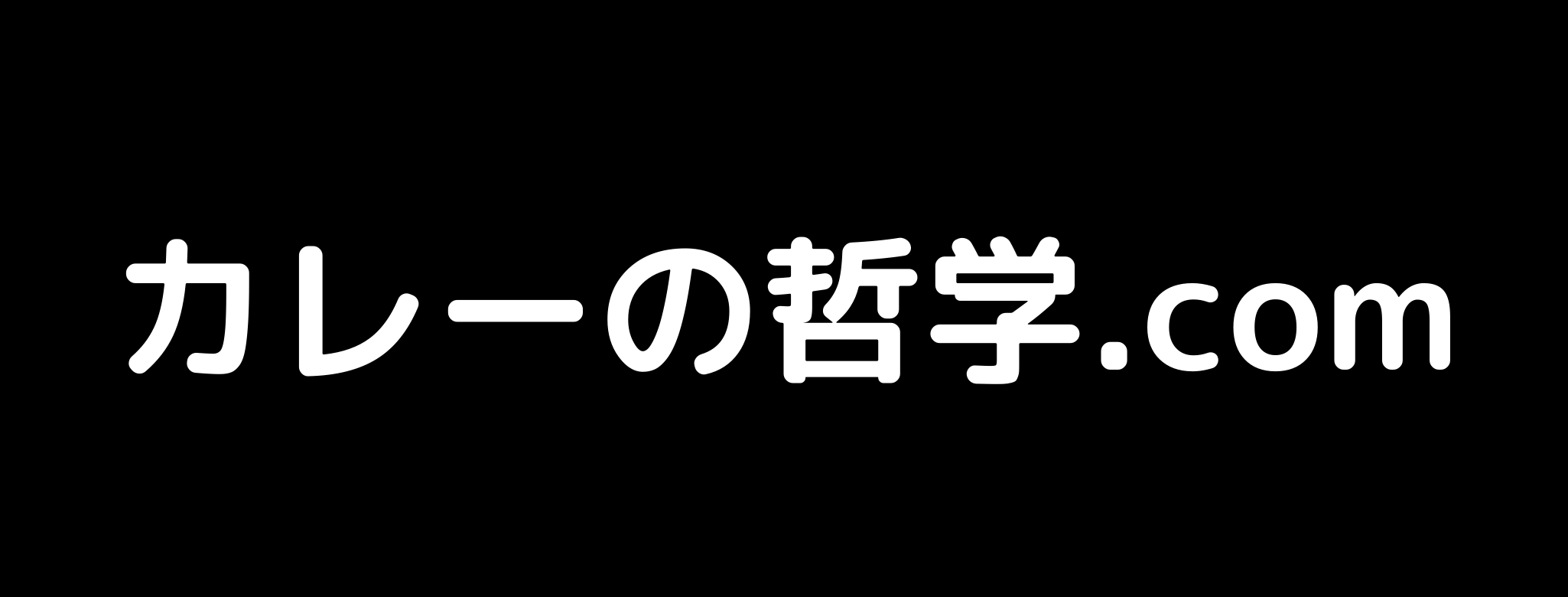
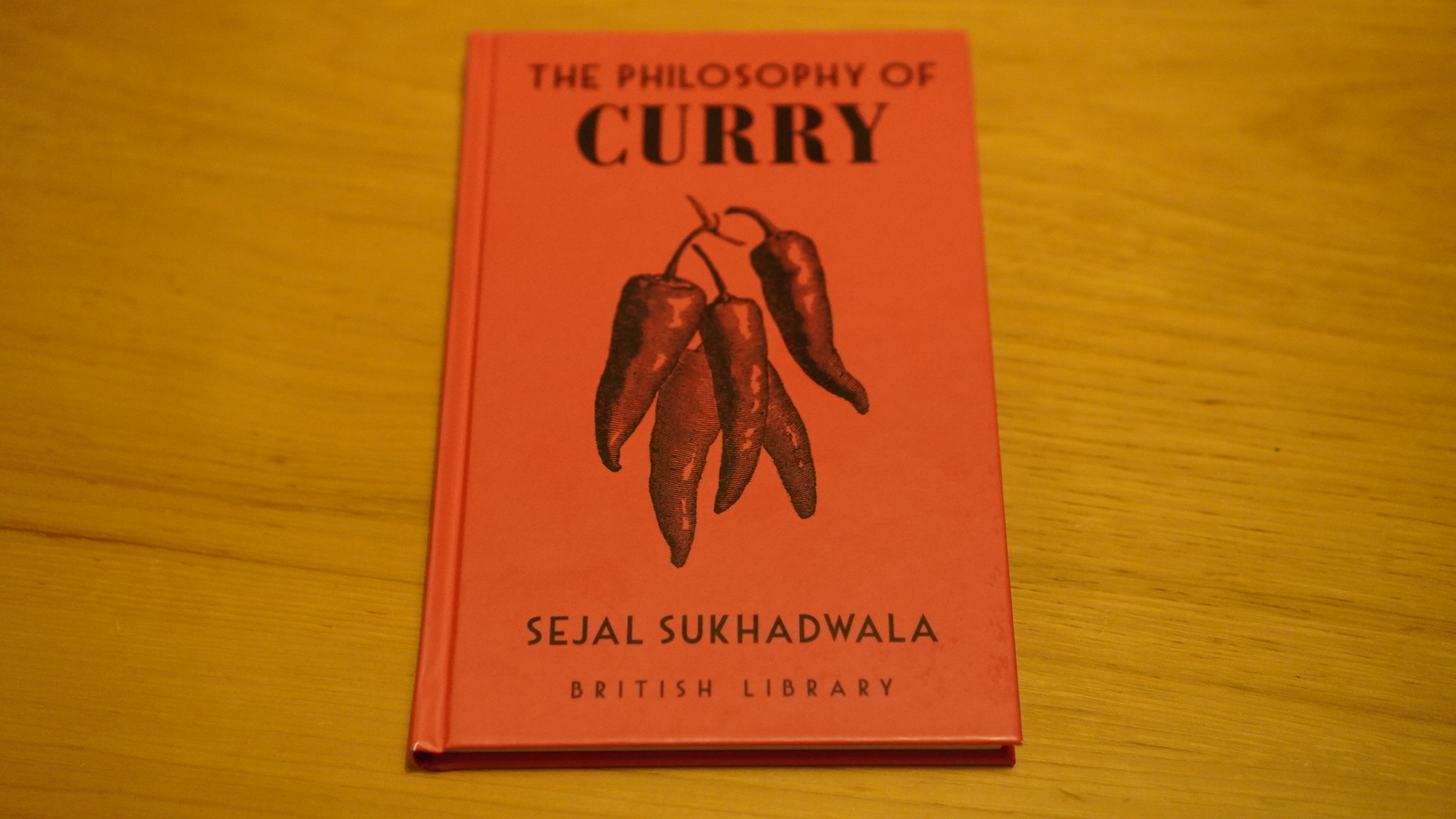



コメント