読んで面白かった本、考えさせられた本などを読書メモがわりに記録しています。
オルダス・ハックスリーの『知覚の扉』を読んだ。ハクスリーはとても百科全書的に教養が深く、話題が美術史の話から音楽の話、ベルグソンの偏在精神の話から禅の話まであちこちに飛びながら人間の「意識の拡張」の論を進めて行く。ドラッグキメてるだけの体験談なのに、とても勉強になる本である。
書かれたのは1954年であるからもはや古典なのかもしれないが、その内容は現代でも通じるところがある。流石に「偏在精神」の箇所などはスピっているように感じるが、決して全て的外れなことを言っているわけではないと思った。
どんな本か:「意識革命」の火付け役ともなった問題作
小説家・思想家のオルダス・ハクスリーがある種のサボテンから抽出される幻覚剤メスカリンを摂取する実験のモルモットとなることを自ら申し出た。本書はその時の知覚の変化体験を詳細に記述・考察したドラッグエッセイ。ハクスリーはヨーロッパで科学者を多く輩出している名家の生まれで、後にカルフォルニアに移住。この本が1960年代のサイケデリック・ムーブメントに与えた影響は大きい。
『知覚の扉』の原題は“The doors of perception“であり、”The doors”のバンド名の元ネタらしい。Hello, I love you tell me your name.
まあこの辺りのことは少し調べたら誰でもわかるのだが、「サイケデリック」という言葉自体がハクスリーと精神科医ハンフリー・オズモンドとの文通の中で生み出されたと造語だというのは初めて知った。
引用:印象に残った箇所
空間はいぜんとして存在したわけである。が、支配的なものではなくなっていたのだ。精神がもっぱら係っていたのは多きさとか位置ではなく、存在と意味だったのである。
河村錠一郎訳,平凡社ライブラリー,『知覚の扉』,p.22
メスカリンを摂取して1時間半。すっかりキマってしまったハクスリーに、実験者が空間関係について質問をした場面。空間が認識できなくなったわけではなく、通常通りに歩いたりすることはできるが、空間には無関心になっていた。また、時間に関しても完璧に無関心になり、「時計は別の世界のもの」になってしまっていた。
人間は、自らのうちに埋め込まれた時間と空間のカテゴリーに当てはめることで世界を認識している。それは相対的な枠組みであるし、生命を維持して行くために必要なことだ。しかし、キマッてしまったハクスリーは永遠の現在に留まり、全てがうちなる輝きで満たされている絶対的な世界に張り込んだ。さらには竹でできた椅子の脚を見つめるうちに、「現実に私が脚そのもの」であると確信していた。ヤバイ。
この体験を考察するハクスリーは、アンリ・ベルクソンの提唱した「偏在精神」の理論に共感する。それは、知覚は「引き算である」というものだ。人間は潜在的には全宇宙の出来事の全てを全て知覚することができるが、あまりにも巨大な情報量のため、そのまま受け取っていると動物としての生存が難しい。脳や神経系は、その情報を取捨選択する「減量バルブ(蛇口)」の役割を果たしている。
人間はこのバルブを通されて出てきたわずか一滴の減量された意識を与えられ、それが意識だと思い込んでいる。言語とは、その中で知覚された意識内容に形を与え表現するシンボリック・システムである。言語があるおかげで他者との意思疎通ができる代わりに、言語のせいでいろいろなものが見えなくなってしまっているのだ。
ハクスリーが見たものは、概念も目的もない、存在それ自体として充足した「永遠の美」だったのかもしれない。
感想:彼岸のカレーを感じたい
偏在精神の箇所は、わかるようなわからないような。足し算の知覚と引き算の知覚、両方を念頭において脳科学とかを調べて見てみたら面白いかも。
物自体という「向こう側(彼岸)の景色」を見る方法がいくつかあって、それはお手軽にはドラッグだったり、禅などの精神修行かもしれない。脳内に何らかの化学的作用が起こった結果として蛇口が緩み、概念に縛られないリアリティを見てしまうということだろう。
悟りを開いた人というのはそういう蛇口を自在に開け閉めすることができ、自在にキマる時はキマり、生活に必要なことをする時はしっかり締めることができるのだ、というようなことも書いてあった。メリハリのついた悟り、そんなことができるようになったら結構楽しそうだ。
昼間は平凡な会社員、アフター5は悟りを開く。
悟り開いちゃったのになんで会社員やっているの?いや、悟っているからこそ会社員をやっているのだ。と言われたら説得力が増す気がする。
欲望とは何か。目的を達成したいと願うことである。何かと何か、例えば自分と他人や過去の自分と今の自分を比べるからそこに目的が生まれるのである。存在自体で充足しているものに目的も成長も何もない。でも、美しいだけじゃ生きていけないよなあ。
言語でもって意味づけることは世界を貧しくすること。規定することは否定することだ。どう頑張ってもリアリティ全体を感じることなんかできない。
「カレー」という言葉があるおかげで我々はカレーを認識できている。しかし、カレー全体を感じたい、カレーになりたいと願ったとしても、言語で相対化している限り我々はカレーになることはできない。そのジレンマは構造的なもので、解消することはできない。いや、問い自体が間違っているのだろう。
そんなことを考えた。
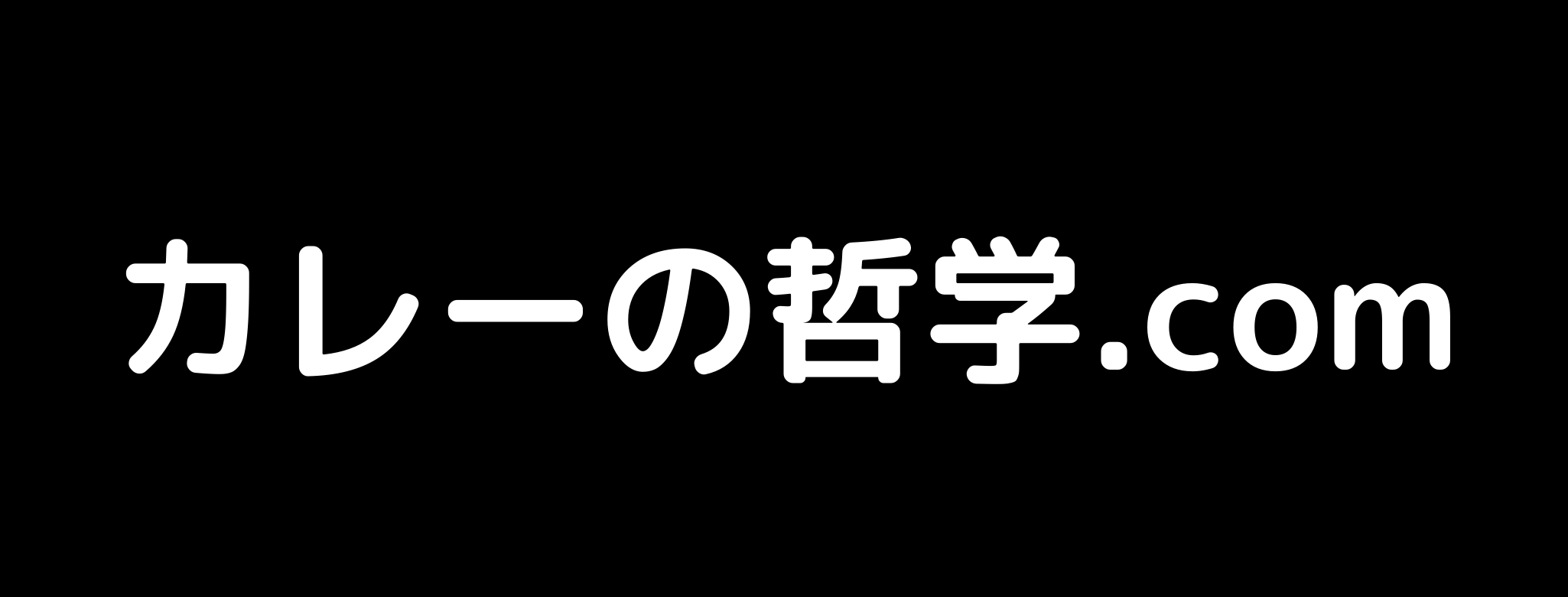
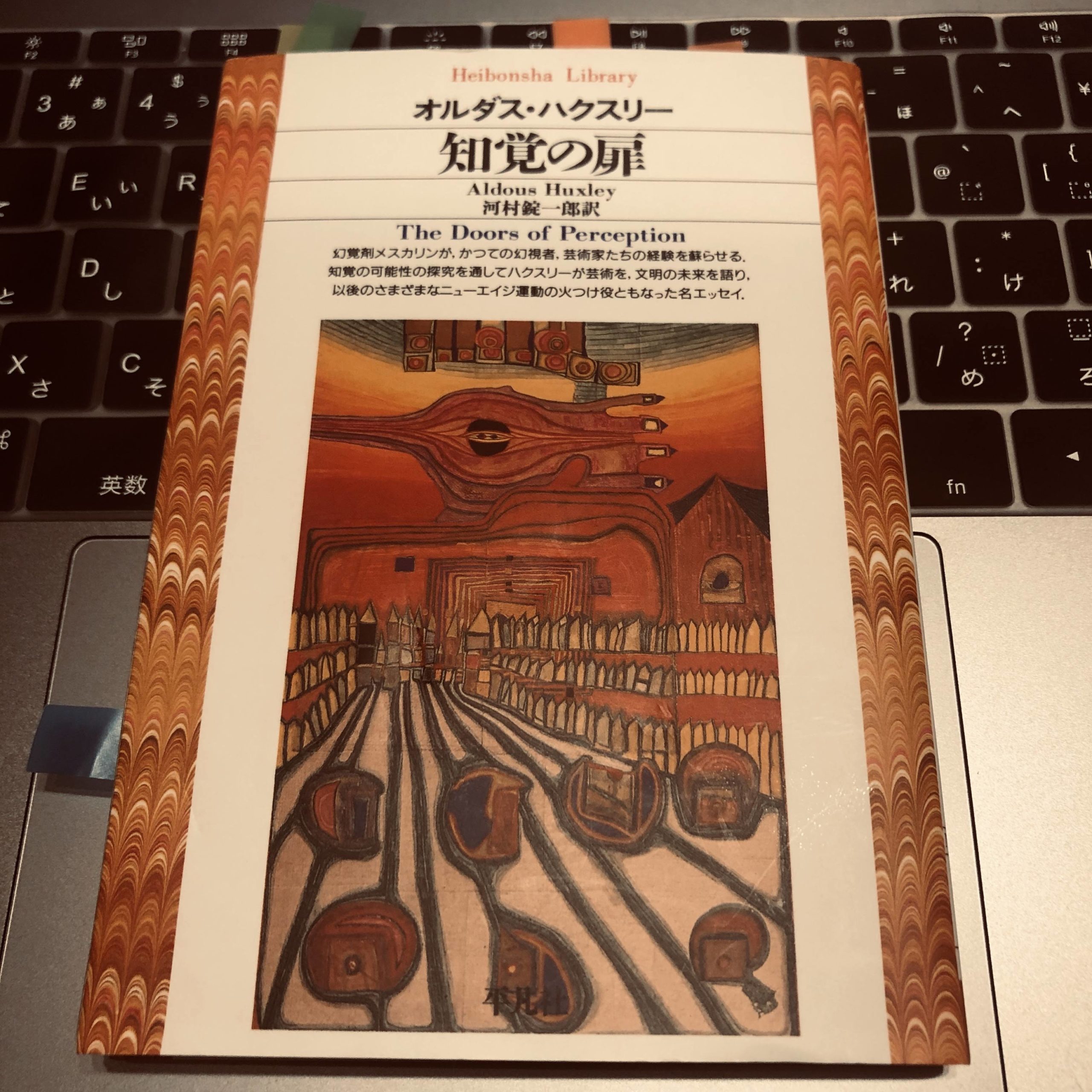



コメント